「預金」をそのままデジタルで動かす。
派手さはないのに、実務が一気に変わるタイプの変革が、ついに最大の預金基盤から来ます。
ゆうちょ銀行は、ディーカレットDCP(DeCurret DCP)のプラットフォームを活用し、2026年度中の「トークン化預金」提供を検討すると発表。
まずはNFTやセキュリティトークン(ST)の取引に連動した決済から段階導入する計画です。
発行体はゆうちょ銀行、形態は決済用預金(預金保険の対象)。
これが意味するのは、約1.2億口座/約190兆円のマネーが、プログラマブルに証券やデータと同時に動くレールへ接続される可能性です。
※ 本記事の情報は2025年9月時点の公開資料に基づいています。提供内容・料金・仕様・規制は 変更される場合があります。最新の情報は各公式サイト・プレスリリース・規制当局の発表をご確認ください。
いま何が起きた?(3行要約)
ゆうちょ銀行が正式発表
ディーカレットDCPのプラットフォームを使い、2026年度中の「トークン化預金」取扱い開始を検討。
まずはNFT/ST決済から段階導入。
発行体はゆうちょ銀行、決済用預金=預金保険の対象。
国内メディアも一斉報道。
DCJPY基盤の活用として解説。
ゆうちょの規模は約1.2億口座/貯金約190兆円。
実装が限定用途でもネットワーク効果のポテンシャルは大きい。
DCJPYとは?最速理解
DCJPYは、ディーカレットDCPが推進する銀行発行のプログラマブル・マネー。
フィナンシャルゾーン(銀行が残高管理・発行・償却)とビジネスゾーン(事業者がユースケース実装)という二層構造で、資金とアセット(証券・NFT・環境価値など)をスマートコントラクトで連携させやすい設計です。
このモデルは「トークン化預金(Deposit Token)」に該当します。
発行体は銀行で、預金としての取り扱い・預金保険の枠組みの下に置かれる点が大きな特徴です。
一方、信託型などのステーブルコイン(資金決済法上の「電子決済手段」)は預金そのものではなく、発行体・仲介者に別の制度設計が適用されます。
トークン化預金
銀行の預金債権をトークンで表現し、ブロックチェーン上で転々流通できるようにしたもの。
銀行マネーのデジタル化。
電子決済手段(ステーブルコイン)
資金決済法の新設枠。信託会社・資金移動業者等が発行主体となる仕組みがあり、銀行預金そのものではない。
誰が得をする?(ステークホルダー別メリデメ)
個人投資家
ST(不動産・社債等)やNFTのDVP(同時履行)決済がしやすくなり、資金・証券の受け渡しを同期。
日次から分・秒レベルへの決済短縮が期待。
預金保険の安心感を伴う銀行マネー起点で参加しやすい。
発行体・証券会社
DVP標準化により決済リスク縮小、清算効率化、発行・流通コストの圧縮余地。
DCJPY連携の実証でも、銀行送金とデジタル証券台帳の突合でT+1〜T+0の短縮可能性が示唆。
事業会社/Web3事業者
- 課金・サブスク・ポイント、RWA(環境価値等)と自動決済の設計が容易に。
IIJ×GMOあおぞら×DCPの環境価値案件は商用化の先行例。
銀行・インフラ側
KYC/AMLやマネロン対策を銀行水準で一体運用しやすい。
法整備(電子決済手段)との棲み分けが進み、ユースケースごとの適材適所が描きやすい。
留意点(みんなの共通課題)
チェーン間接続・相互運用性、障害時の償還オペレーション、ウォレットUX(誤送金・鍵管理)、手数料設計の実装ディテールはこれから。
公式リリースには料金の具体記載なし(一部メディアは推測表現あり)。
産業インパクト:5つの焦点
- STO市場(デジタル証券)
DVPの一般化でSTの発行・流通の詰まりが解けやすくなる。
BOOSTRY(ibet for Fin)系の実証では銀行口座×デジタル債のDVPスキームを立証。
DCJPY連携の汎用性もテスト環境で確認済み。 - RWA(環境価値・サプライチェーン)
環境価値のデジタルアセット×自動決済というデータ連動決済が商用化の先行事例に。
銀行がミンティングを担うことで会計・与信・監査面の説明がしやすい。 - 小売・ポイント・会員経済圏
お金とデータが同じタイムラインで動くとロイヤルティ設計が変わる。
二層構造で事業者側のロジックを柔軟に実装。 - 企業決済・越境
将来の外部チェーン連結や、他方式(信託型SC等)とのPVP/DVP相互運用が焦点。
メガバンク陣営のステーブルコイン実証も進行中で、方式間連携の実務標準づくりが勝負所。 - 規制優位と実装速度
日本は電子決済手段(ステーブルコイン)の枠組みを先行整備。
トークン化預金との役割分担が進み、安全性×利便性の両立で実装しやすい土壌がある。
いつ広がる?(タイムラインとチェックポイント)
- 2025年〜:DVP等の実証から商用手順の磨き上げ。
DCJPYは既に環境価値の決済で実務稼働実績あり(GMOあおぞらが発行銀行として参画)。 - 2026年度中:ゆうちょがNFT/ST決済から段階導入(まずは特定ユースケース中心の見込み)。
個人・法人向けと明記。 - 2027–2028(見通し):請求・サプライチェーン・自治体給付などへ適用範囲が拡大。
課題は相互運用性・UX/ガバナンス・会計/税務の運用整理。
根拠は二層構造の外部連結方針と既存PoCの方向。
競合マップ&相互運用
Progmat Coin(MUFG系)
信託型ステーブルコイン等の発行基盤。
RWA/国際送金のユースケースを志向。
SMBC×Fireblocks×Ava Labs×TIS
ホールセール決済・RWAを中心にステーブルコインの事業化検討を開始。
DCJPYの強み
預金そのもののトークン化、銀行勘定・預金保険の枠、二層構造による業務連携のしやすさ。
争点:DVP/PVPの相互運用(方式間ブリッジ、共通メッセージング)、規制アービトラージ回避、障害時の統一的リカバリ手順。
投資家の視点(テーマ整理として)
免責:本稿は情報提供であり、特定銘柄の推奨・勧誘ではありません。投資判断はご自身で。
リスクと論点
- 制度面:トークン化預金と電子決済手段(ステーブルコイン)の境界運用、仲介業規制、AML/CFT。
金融庁・日銀の資料で論点整理が進むが、会計・税務の実務定着はこれから。 - 技術・運用:チェーン間接続・可用性・スマコン脆弱性。障害時の償還・巻き戻しや誤送金リスク。
- UX/料金:公式リリースに手数料の明示はなし。
メディアの記述は推測・先行事例の援用が含まれる点に注意。
まとめ
- ゆうちょ×DCJPYは、銀行預金のまま動くデジタル決済レールを大規模に普及させる起爆剤。
まずはNFT/ST決済から。 - STO/RWAの実装に直結し、DVPの普及で市場の回転を高める。
- 勝敗を分けるのは相互運用性×UX。
方式間ブリッジと使いやすさを制した陣営が主流になる。
付録【基本Q&A・用語解説】
基本Q&A
Q. これはステーブルコインですか?
A. いいえ。トークン化預金です(銀行預金をトークン化)。一方、信託型等の電子決済手段(ステーブルコイン)は預金そのものではない別制度。用途に応じて併存・連携します。
Q. 一般ユーザーがすぐに自由送金できますか?
A. 公式発表はNFT/STの決済からの段階導入。一般的なP2P送金や小売決済の詳細・手数料は現時点非開示です。
Q. 先行する実運用はありますか?
A. 環境価値の取引・決済で、GMOあおぞらネット銀行がDCJPYの発行銀行として参画し商用開始済み。
Q.DCJPY と JPYC は何が違うの?
A. いちばん大きな違いは「発行主体」と「法的な位置づけ」です。
DCJPY(ゆうちょ等のトークン化預金)は、銀行が発行する預金そのもののデジタル版。
ゆうちょ銀行のケースでは決済用預金として預金保険の対象になる設計で、まずNFT/ST決済から導入予定です。
基盤はディーカレットDCPの許可制(パーミッションド)ネットワーク。
JPYC(電子決済手段=ステーブルコイン)は、JPYC株式会社が資金移動業者として発行する円連動トークン。日本円(預貯金や国債)で保全され、1:1での償還が可能。Ethereum/Polygon/Avalancheで発行予定です。
従来のJPYC Prepaid(前払式支払手段)とは別トークンで、相互交換は不可と明記されています。
クイック比較
| 観点 | DCJPY(トークン化預金) | JPYC(電子決済手段・ステーブルコイン) |
|---|---|---|
| 発行主体 | 銀行(例:ゆうちょ銀行が発行体) | JPYC株式会社(資金移動業者として発行) |
| 法的な位置づけ | 預金のトークン化(決済用預金は預金保険対象) | 資金決済法の「電子決済手段」(預金ではない) |
| 裏付け資産 | 銀行預金(口座残高と1:1) | 日本円(預貯金)や国債で保全、1:1償還 |
| ネットワーク | 許可制(DeCurret DCP の二層構造:フィナンシャル/ビジネス) | パブリックチェーン(Ethereum/Polygon/Avalanche) |
| 主な開始用途 | NFT・STのDVP(同時履行)決済から | 送金・決済・Web3連携の広範ユースケース |
| KYC/AML | 銀行レベル(口座ベースで統合管理) | 資金移動業の枠組みで実施 |
| その他 | 銀行システム直結で会計・監査に説明しやすい | 既存ウォレット/DAppと相性良。JPYC Prepaidとは別トークン(相互交換不可) |
上表は2025年9月1日時点の公開情報を基に作成しています。
実装や提供範囲、手数料の詳細は今後の開示で更新される可能性があります。
用語解説(かんたん&実務に使える版)—表形式
| 用語 | ひとことで | 実務ポイント | 代表ユースケース |
|---|---|---|---|
| DCJPY | 銀行が発行する円のデジタル版を、プログラムで動かせる基盤 | 二層構造(下=お金のレール/上=アプリ層)。トークン化預金として運用可。API/スマコン連携 | NFT決済同期、STのDVP、環境価値の自動決済 |
| トークン化預金(Deposit Token) | 預金そのものをトークン化したもの | 発行体=銀行。原則預金保険の枠。KYC/AMLは銀行水準。会計・税務は実装で要確認 | 給与/家賃の自動送金、ST即時決済、企業間自動決済 |
| 電子決済手段(ステーブルコイン) | 法制度上の価格安定型トークン(預金ではない) | 信託型など資金決済法の枠。保全/発行主体が預金と異なる。相互運用や両替レール設計が肝 | EC決済、国際送金、クリプト/法定通貨ブリッジ |
| DVP(Delivery vs Payment) | 受け渡しと支払いを同時に完了 | 決済リスク低減、清算効率化。スマコンで同時履行を自動化しやすい | ST受渡し、社債/不動産トークン購入、チケット安全取引 |
| フィナンシャルゾーン | DCJPYの下層:お金のレール | 銀行が発行・送金・償還やKYC/AMLを担当。高可用性/復旧手順が前提 | 口座/残高管理、送金オーケストレーション、監査対応 |
| ビジネスゾーン | DCJPYの上層:アプリ層 | 事業者が業務ロジックを実装。上層は自由度、下層は安全性を担保 | NFT販売、RWA管理、サブスク/ポイント、自動請求 |
| スマートコントラクト | 条件付き支払いを自動実行するプログラム | 「◯日になったら支払う」「資産が届いたら支払う」をコード化。ログが残り監査に強い | 家賃/給与の自動振替、DVP/PVP同時決済、保険金自動支払 |
| STO / ST | 証券のデジタル版(発行=STO、証券トークン=ST) | DVPでT+0/T+1短縮、少額化・24/7運用。カストディ/適格要件は要確認 | 不動産・社債・私募債のデジタル発行/流通 |
| RWA(Real World Asset) | 現実資産のトークン化 | 裏付け・評価・監査・オラクルが要。データ×決済連動で自動支払いを設計 | 環境価値(REC)、売掛債権、在庫金融、不動産収益分配 |
| PVP(Payment vs Payment) | 通貨同士を同時交換 | 為替/ステーブル間の相互運用の要。ブリッジ/メッセージ規格の整合が重要 | クロスチェーン/越境送金、銀行間FX決済 |
| KYC/AML | 本人確認とマネロン対策 | 取引時・継続的CDD、トランザクション監視、疑わしい取引の届出。UXと法令順守の両立 | 口座開設、トークン送金の審査、事業者のコンプラ運用 |
本記事は情報提供を目的としたもので、特定の投資行為の助言ではありません。市場・制度・技術の変更により内容が 変わる可能性があります。投資はご自身の判断と責任で行ってください。
参考資料・引用元
- ディーカレットDCP 公式プレスリリース(2025/09/01): 「ゆうちょ銀行におけるトークン化預金の取扱に向けた検討について」
- PR TIMES(ディーカレットDCP、2025/09/01): 同上発表
- Impress Watch(2025/09/01): 「ゆうちょ銀行、『トークン化預金』26年度提供へ」 / ケータイ Watch(2025/09/01): 関連報道
- CoinDesk Japan(2025/09/01): 「ゆうちょ銀行、トークン化預金の導入を正式発表──DCJPY活用」
- DCJPYの二層構造(公式): 解説ページ / ブローシャPDF
- 環境価値×DCJPY(商用案件の先行例): IIJ等 共同発表(2024/08/28) / GMOあおぞらネット銀行(2023/10/12)
- JPYC(資金移動業・電子決済手段): 資金移動業者登録の発表(2025/08/18) / Impress報道(2025/08/19) / CoinDesk Japan(速報)

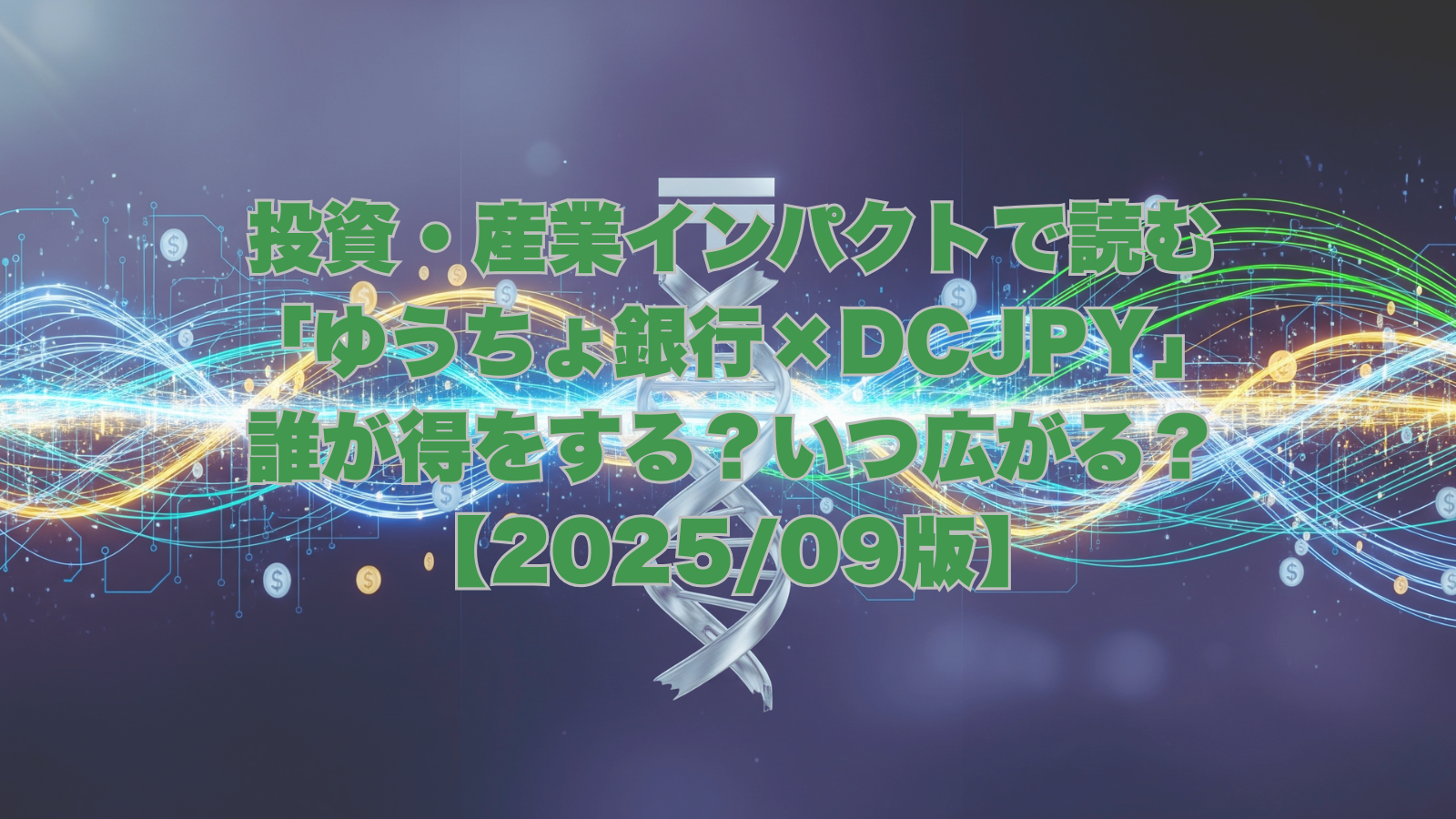
-300x169.webp)





-300x169.webp)
