「便利そうだから」と始めた暗号資産P2P取引。
その裏側には、あなたの銀行口座が突然ロックされ、数ヶ月間、預金を引き出せなくなるという、日本特有の「落とし穴」があります。
「自分は詐欺とは無関係だ」と思っていても、知らない間に被害者と加害者をつなぐマネーロンダリングの「中継役」にされてしまうのがP2Pの現実です。
特に2024年2月以降、警察庁の要請により日本の金融機関の監視は劇的に強化されています。
本記事では、悪意なく巻き込まれた際にあなたの生活を守るための『自衛ルール』と、万一の事態にパニックを避ける『凍結時72時間アクション』を徹底解説します。
大切な資産と生活を守るために、まずこの現実を知ってください。
安心な生活を守るために知っておくべき日本の現実と対策
手数料を抑えてすばやく換金できるP2P取引は便利に見えます。
しかし、日本では振込名義の不一致や不自然な入出金の連鎖が、銀行の監視で高リスク取引として検知され、凍結や調査につながることがあります。
悪意がなくても巻き込まれる可能性があるからこそ、仕組みと対策を先に理解しておくことが大切です。
重要:日本では名義不一致の送金が厳しく見られています
警察庁は2024年2月7日、暗号資産交換業者あての送金で振込名義の不一致などが判明した場合、金融機関が取引を拒否・強化するよう要請しています。
P2Pでは第三者名義の振込や短時間の資金移動が起こりやすく、口座凍結や調査につながるリスクが高いことを前提に行動しましょう。
日本におけるP2Pの特有リスク(なぜ口座が凍結されるのか)
日本では、詐欺被害金が自分の口座に混入した疑いが生じると、金融機関は被害回復を前提に口座をいったん止める。
根拠は、振り込め詐欺救済法と監督指針に基づく対応であり、恣意的な処分ではない。
P2P取引は構造的に、名義不一致の入金、第三者名義からの振込、短時間での入出金や少額分割などが起こりやすい。
金融機関と交換業者は、犯罪収益移転防止法に基づくモニタリングと疑わしい取引の届出義務を負い、これらの挙動を高リスクとして強く警戒する。
凍結後は、銀行による取引停止や照会の後、預金保険機構の公告と申出期間を経て、被害者への分配または解除という流れで進む。
期間中は残高の移動に制約が生じることがある。
正当性を示すエビデンスが整理されていれば、解除判断の後押しになる。
巻き込まれ防止の要点は、名義一致の厳守、着金の事実確認、プラットフォーム内チャットの三つ。
詳細は後続の「自衛ルール」と「凍結時72時間アクション」で具体化する。
P2Pでよくある手口の実態
偽の入金スクリーンショットを見せて暗号資産の解放を急がせる、チャット外へ誘導して証拠を残さない、名義不一致の口座から振り込ませるなど、典型的なパターンがあります。
国内向けにも、主要取引所はこうした事例と予防策を公開しています。
初心者が最初に決めておく「自衛ルール」
名義一致の原則
取引相手のKYC氏名と、振込口座名義が完全一致する場合のみ受領する方針を最初から決める。少しでも不一致や不自然があれば即キャンセルとサポート介入を申請する。
チャットは必ずプラットフォーム内
やり取りは取引所の公式チャットに限定し、外部SNSやメッセージアプリに移らない。紛争時の証跡確保のため。
入金確認前の暗号解放は絶対にしない
銀行アプリで着金を自分の目で確認する。入金証明の画像だけでは解放しない。
専用口座と取引設計
P2P専用の受取口座を用意し、日常口座と分離する。頻繁な少額の出し入れを続ける運用は避け、監視システムに不自然と見なされないように設計する。
不審シグナルが出たらすぐに異議申立て
少しでも違和感があれば、取引所で異議申立てや介入を申請する。
偽の「自動支払い」や外部連絡先の提示などは赤信号。
🚨 すぐ使える「凍結時72時間アクション」チェックリスト
緊急時にパニックにならないよう、以下の手順をそのまま上から実行してください。
【💻 証拠保全】
□ 銀行の着金通知、入出金明細を時刻が分かるようにスクリーンショットで保存。
□ P2P取引の相手KYC表示名、注文ID、取引所内チャット履歴、TXハッシュをエクスポートして保存。
□ 端末のシステム時刻・アプリ通知ログ・ブラウザ履歴など、時間軸確認に役立つログも保存。
□ 保存ファイルは日付_案件名のフォルダで整理し、変更不可のPDFやPNGで複製を作成。
【🏦 銀行への連絡】
□ まずは自分の取引支店またはコールセンターへ連絡し、凍結の有無と範囲(入出金・残高照会など)を確認。
□ 凍結理由の説明可否、凍結理由コード(あれば)を確認し、メモを作成。
□ 担当部署名、担当者名、通話日時、問い合わせ番号を記録。
□ 提出依頼書類の一覧(取引明細、身分証、経緯説明書など)を入手し、提出期限と提出先を控える。
【📞 警察への相談】
□ 最寄りの警察署または警察相談専用電話 #9110 に相談。
□ 被害回復手続の見通し、提供すべき証拠の範囲、相談受理番号(または対応記録)を確認。
□ 取引所サポートへの同報連絡の要否や推奨文言を確認。
【🔍 監視と状況把握】
□ 預金保険機構の公告サイトで自分の口座が掲示されていないかを継続的に確認。
□ 取引所の紛争解決フロー(エスクロー、異議申立て、仲裁)を確認し、必要書類を準備。
□ 経緯のタイムライン(日時・イベント・証拠の在りか)を簡潔に作成。
【📦 提出用パッケージの作成】
□ 経緯説明書(A4 1枚)を作成。時系列、関係者、金額、取った対応を簡潔に記述。
□ 添付資料一覧を作成し、各ファイルに連番と簡易タイトルを付与(例 01_入金明細_2025-11-10.png)。
□ Zip化した提出パッケージと、編集不可のPDF版をそれぞれ用意。
【🛡️ 再発防止の初期設定】
□ 名義一致ルールの徹底、外部チャット禁止、入金確認前の解放禁止を文書化。
□ P2P専用口座の分離、少額連続入出金の抑制、入金元の記録を標準運用に追加。
時間帯別の行動目安
直後(0〜2時間)
□ 証拠保全と連絡日誌の開始。銀行・取引所・警察の順に一次連絡。
初日(2〜24時間)
□ 銀行に提出物の下準備。経緯説明書の骨子を作成。取引所へ介入申請。
2日目(24〜48時間)
□ 追加で求められたエビデンスを整備。公告サイトの確認を継続。
3日目(48〜72時間)
□ 提出物を期限内に送付し、到達確認。タイムラインを更新し、次の連絡予定日を設定。
万一、口座が凍結されたときの行動フロー
最初に銀行へ連絡し、凍結理由の確認と必要書類を整理する。
次に警察へ相談し、事情説明と証拠の提供準備を進める。
サポート窓口の連絡先や相談番号は以下。
着手すること
取引所内チャット、相手のKYC情報、注文ID、トランザクションハッシュ、入出金明細、端末ログをすべて保存する。預金保険機構の公告サイトで自分の口座が手続きに入っていないかを検索し、進行状況を把握する。
法制度の理解
振込被害の回復は、銀行の凍結後に公告、意見申立て、分配という段階で進む。時間軸があるため、早い段階で相談と証拠保全に動くことが結果を左右する。
注意点
口座・カード・ネットバンキング情報の売買や譲渡は犯罪。
安易な名義貸しやアカウントの共有は絶対にしない。
リスク早見表
| 状況 | よくあるリスク | その場で取る行動 | 根拠・参照 |
|---|---|---|---|
| 相手が入金済みと主張 | 偽の支払い証明 | 自分の銀行アプリで入金確認が出るまで暗号を解放しない | 取引所の注意喚起に一致 |
| 口座名義が相手KYCと不一致 | 名義不一致は監視強化・拒否の対象 | 取引を中止しサポート介入を要請 | 警察庁の要請公表 |
| 少額の入出金を頻発 | モニタリングで不自然判定 | 取引設計を見直し、専用口座で集約 | 取引所の運用ガイド |
| 凍結を告げられた | 被害回復手続へ移行の可能性 | 銀行に事実確認、警察相談、証拠保全 | 金融庁・預金保険機構の案内 |
凍結時の連絡先メモ
警察相談専用電話は「#9110」。
金融サービス一般の相談は金融庁の利用者相談室が案内している。
平日の日中に電話窓口が中心。
| 相談先 | 主な用途 | 電話 | 受付時間 | 公式URL |
|---|---|---|---|---|
| お使いの銀行 コールセンター/取引支店 | 凍結の有無と範囲の確認、凍結理由や理由コードの照会、提出書類と期限の案内、解除手続の確認。最初に連絡すべき窓口 | キャッシュカード裏面の番号/各行コールセンター(カード・通帳紛失等は24時間の専用ダイヤルがある場合あり) | 平日9:00〜17:00が多い。紛失・盗難の緊急停止は多くの銀行で24時間 | 各行公式サイトの「お問い合わせ」ページ(例:〇〇銀行 お問い合わせ) |
| 警察相談専用電話(#9110) | 緊急ではない警察相談全般。発信地の都道府県警の相談窓口につながる | #9110 | 各都道府県警の運用に準拠(夜間・土日祝は当直や音声案内の場合あり) | https://www.npa.go.jp/goiken_index.html |
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | 金融サービス一般の相談(暗号資産を含む) | 0570-016811(ナビダイヤル)/IP電話 03-5251-6811 | 平日10:00〜17:00 | https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html |
| 預金保険機構「振り込め詐欺救済法」公告サイト | 口座凍結後の公告・手続状況の検索 | ー | ウェブで随時確認可 | https://furikomesagi.dic.go.jp/ |
| 日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)苦情相談 | 交換業者(会員社)との個別トラブル相談 | 03-3222-1061 | 月〜金 9:30〜17:30(祝日・年末年始除く) | https://jvcea.or.jp/contact/ |
| 参考:各都道府県警 相談番号一覧 | #9110が使えない回線等での個別番号一覧 | ー | ー | https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/soudan/soudanmadoguti.pdf |
使い方のひとこと
凍結に気付いたら、まず銀行に連絡して事実確認と必要書類を把握し、次に#9110や取引所サポートへ展開する順番が最もスムーズです。
ケーススタディ
SNSやブログでは、P2Pの売買相手が詐欺グループで、被害者の日本円が自分の口座に振り込まれて口座凍結と調査に至ったという複数の報告がある。
真偽や個別事情の精査は必要だが、名義不一致や外部チャット誘導、偽の入金証憑といったシグナルが共通する。
用語のメモ(簡易用語集)
P2P
取引所のエスクローを介し、個人間で法定通貨と暗号資産を交換する仕組み。
名義不一致
送金人の口座名義と、取引で認証した氏名が一致しないこと。銀行や交換業者の監視対象。
振り込め詐欺救済法
詐欺被害金が振り込まれた口座の残高から、被害者に分配するための手続を定める法律。
疑わしい取引の届出
金融機関等がマネロン等の疑いがある取引を当局へ届出る義務。
免責とお願い
本記事は一般的情報の提供であり、投資助言や個別の法律相談を目的とするものではありません。
個別案件は専門家へ相談してください。

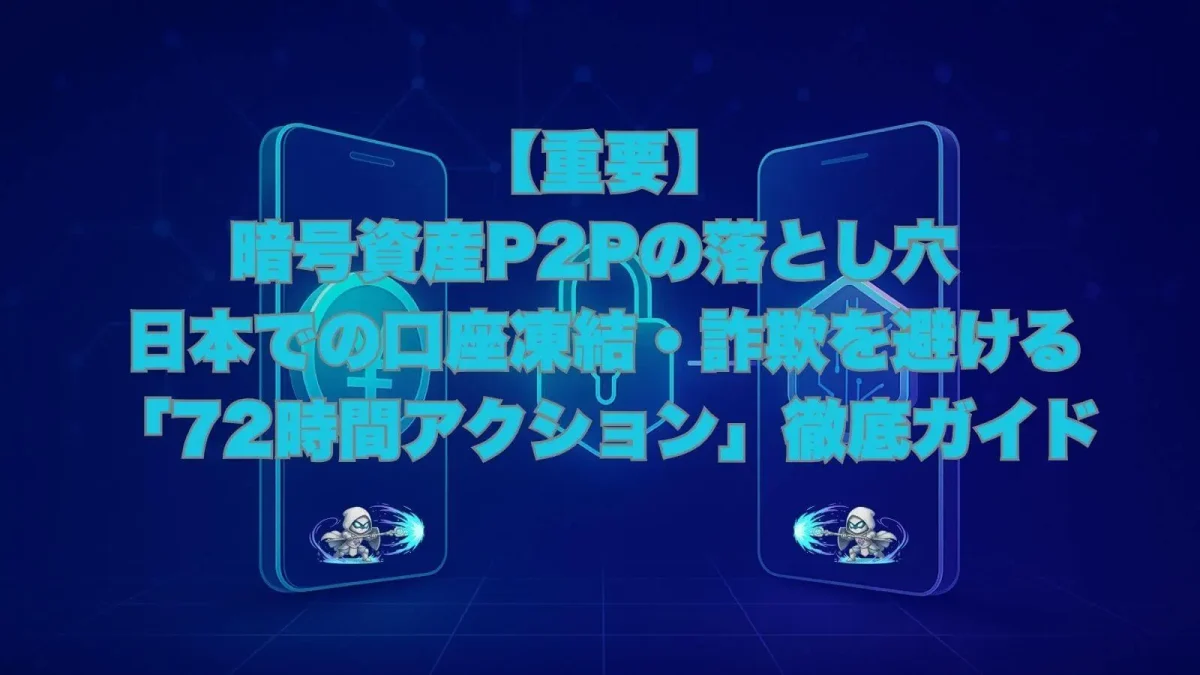
-300x169.webp)




-300x169.webp)

